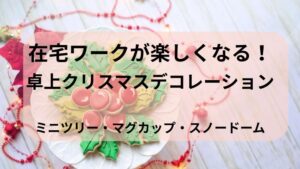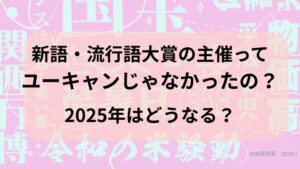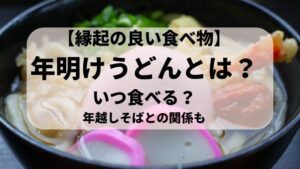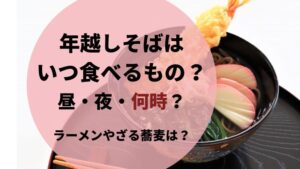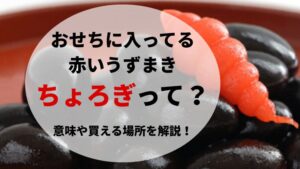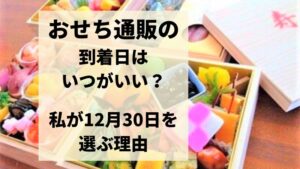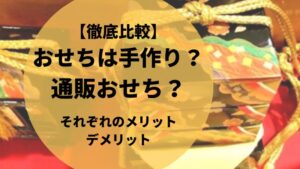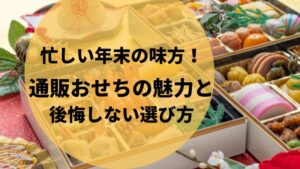おせち料理といえば、三段重の重箱を思い浮かべる人が多いですよね。
実際に市販のおせちの多くも三段重で販売されています。
私自身も長年、「重箱=三段が基本」だと思い込んでいました。
ところが本来、おせちは「幸せを重ねる」という願いを込めた四段重(与の重)が基本なんです。
さらに五段目の「五の重」には、知っておくとちょっと自慢できる“特別な意味”があります。
この記事では、重箱の段ごとの意味と、与の重・五の重に込められた日本の伝統的な考え方を、わかりやすく紹介します。
スポンサーリンク
与の重とは?「四」を避けて“幸せを重ねる”縁起重
重箱は上から順に「一の重」「二の重」「三の重」と数えますが、4段目だけは「四の重」とは呼びません。
その理由は、「四(し)」が「死」を連想させるから。
そこで日本では縁起を担ぎ、「与(よ)」の文字を使って「与の重(よのじゅう)」と呼ばれています。
マンションやホテルで「4号室」が欠番(303号室の隣が305号室)になっているのと同じ発想ですね。
与の重には煮物を詰めるのが基本。
家族の無病息災や子孫繁栄を願う意味が込められています。
各段に詰める料理の意味と役割

重箱には段ごとに詰める料理の種類が決まっており、それぞれに願いが込められています。
- 一の重(祝い肴)
黒豆・数の子・田作り・たたきごぼうなど、お祝いの定番料理。 - 二の重(口取り・酢の物)
紅白かまぼこ・伊達巻・昆布巻・栗きんとん・紅白なます、菊花かぶなど彩り豊かな料理。 - 三の重(焼き物)
鯛やぶりなどの焼き魚、イカの松笠焼、焼きえびなど、めでたさと長寿を象徴。 - 与の重(煮物)
煮しめや煮物を詰め、家族の無病息災や子孫繁栄を願います。
ただし地域や家庭によって料理の内容や詰め方はさまざま。
最近は、子どもが好きな料理や洋風メニューを加えるなど、自由なおせちスタイルも増えています。
でも昔ながらの意味を知っておくと、重箱を詰めるのがもっと楽しくなりますよ。
五の重には何も入れない?「空」に込められた願い
五段重を使う場合、最下段の五の重には料理を詰めず、空のままにするのが正式な作法です。
これは「年神様から授かった福を入れる場所」「福を詰める余白を残す」「来年も多くの幸せを受け入れられるように」という願いが込められています。
つまり、空の五の重は“福を呼び込むためのスペース”なんですね。
5段目の五の重の意味は諸説あるようですが、現代では、「家族の好物を入れる」「多めに作った料理を詰めて保存する」など、実用的なアレンジも一般的になっています。
伝統を守りつつ、家族に合わせた使い方を楽しむのが今のおせちスタイルです。
スポンサーリンク
まとめ|3段だけじゃない「重箱」の奥深い意味
- 重箱の正式な形は、「与の重」を含む4段が基本。
- 四は縁起を避けて「与」と表記し、煮物を詰める。
- 五の重は空にして福を呼ぶのが伝統的な考え方。
おせちは単なるお正月料理ではなく、「福を重ねる」という意味が込められた日本の知恵そのもの。
「三段が当たり前」と思っていた人も、来年は与の重や五の重に少しこだわってみると、お正月がもっと特別なものになるかもしれません。
あわせて読みたい
同じ人数分でも「1段か3段か」で迷ってしまう人は少なくありません。
失敗しない選び方を知っておくと、通販おせち選びがぐっとラクになります。
👉 詳しくはこちら
【通販おせち】1段と3段どっちがいい?同じ人数分でも失敗しない選び方ガイド↗
スポンサーリンク