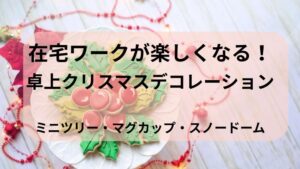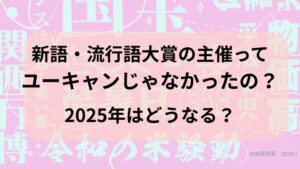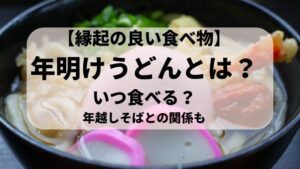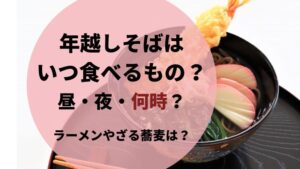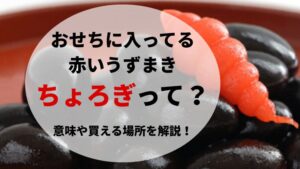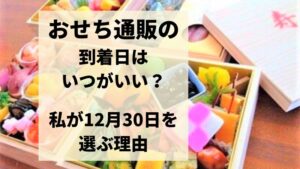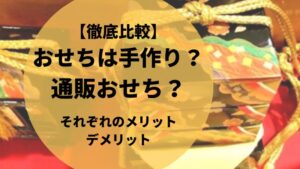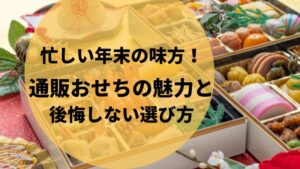9月9日は重陽の節句(ちょうようのせっく)で5節句のうちのひとつで、健康や長寿を願う節句です。
「菊の節句」とも呼ばれ、菊の花を飾ったり、菊酒をいただいたりする風習があります。
桃の節句などに比べるとあまり知られていない日本の伝統行事のひとつです。
スポンサーリンク
重陽の節句ってどんな行事?

9月9日が特別な理由
「重陽の節句(ちょうようのせっく)」は、9月9日に行われる日本の5節句のひとつです。
中国の 陰陽思想では、奇数は「陽(よう)」、偶数は「陰(いん)」とされ、奇数の中で最大の数「9」が重なる9月9日は「陽が重なる=おめでたい日」とされてきました。
そして日本にもこの考えが伝わり、「重陽の節句」として定着しました。
菊の節句と呼ばれる理由
重陽の節句は「菊の節句」とも呼ばれます。これは、菊の花がちょうど見ごろを迎える季節であること、そして昔から菊には「不老長寿」の力があると信じられていたからです。
重陽の節句の前夜に菊の花に綿をかぶせて、翌朝その綿にたまった露で体を拭くと健康で長生きできるといわれていました。
この風習を「菊の着綿(きせわた)」と呼びます。
昔、私が華道と茶道のお稽古に行っていたとき、重陽の節句ころのお茶菓子は菊の練切の着綿(きせわた)でした。
そして花材はもちろん菊でした。
菊の花の色には位がある
菊の色には位があって 白紫黄紅赤。
これは、白い色の位が一番高く、順番に右に行くにつれて位が低くなっていきます。
一番位の高いのは『白色』なんです。
白い菊は高さを一番高く最初にいけます。
白紫黄紅赤は「はくしおうこうせき」と読みます。
この5色の菊をいけるなら一番位の高い白い菊の高さを一番高く、紅赤色の菊は低めに順番にいけていきます。
複数の色の菊に花をいけるときは、心のなかで「はくしおうこうせき」といいながらいけたものです。
スポンサーリンク
重陽の節句と五節句
重陽の節句は「五節句(ごせっく)」と呼ばれる年間の重要な節句のひとつです。五節句は以下の5つ。
| 日付 | 節句名 |
| 1月7日 | 人日(じんじつ) |
| 3月3日 | 上巳(じょうし) |
| 5月5日 | 端午(たんご) |
| 7月7日 | 七夕(しちせき) |
| 9月9日 | 重陽(ちょうよう) |
たとえば、七草がゆやちらし寿司、ひなケーキに柏餅、ちまき、そうめん、星の形をしたゼリーなど、他の節句では行事食がスーパーで大々的に並び、節句にちなんだ手作り料理などもSNSで話題になります。
そして雛人形を飾ったり鯉のぼりをあげたり、短冊に願い事をかいたりと誰もが経験したり見聞きすることの多い行事です。
けれど、重陽の節句に関しては、そうした盛り上がりをあまり見かけません。
特別な商品が並ぶことも少なく、行事として取り上げられる機会も少ないです。
現代でも楽しめる重陽の過ごし方

食用菊・菊酒ってどんなもの?
昔ながらの風習を現代でも手軽に楽しむ方法のひとつが「食用菊」や「菊酒」です。
スーパーなどで売っている食用菊(もってのほか等)を使えば、簡単に重陽の節句を楽しむことができます。
冷やした日本酒に花びらを浮かべた「菊酒」。
菊の香りと見た目の美しさが味わえる、ちょっと贅沢なひとときになります。
また薬膳素材としても知られる胎菊花(たいきくか)は通販で購入できます。
お酒に浸けたり浮かべたり、お湯をそそいだりで簡単に菊酒や菊茶ができあがります。
まとめ

重陽の節句という行事はあまり知られていないものの、長寿や健康を願うすばらしい風習です。
菊を飾ったり、菊モチーフの和菓子を用意するだけでも、重陽の節句らしい雰囲気を楽しめます。
日々の暮らしに、季節の行事を取り入れるのはとてもすてきですね。
スポンサーリンク